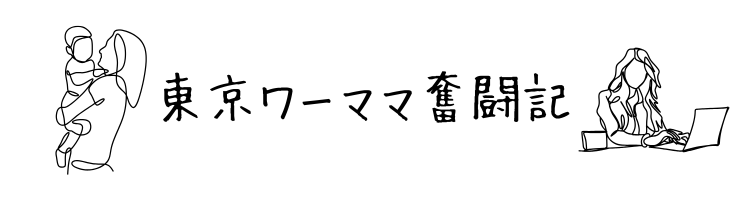共働きが当たり前となった今、子育てと仕事を両立する手段として「時短勤務」を選ぶ人は少なくありません。
私自身もその一人で、長男が小学校に入学するまでの約5年間、時短勤務で働き続けてきました。
ありがたいことに、私が勤めていた会社は産休育休を取得する社員も多く、時短勤務に対して理解がある職場でした。
嫌味を言われることもなく、制度としてはとても恵まれていたと思います。
それでも、日々の中でふと「この働き方、本当に報われているのかな?」と感じる瞬間が何度もありました。
それは私のわがままなのか、それとも社会の仕組みの問題なのか…。
今回は、私が「時短勤務って本当に割に合うの?」と感じた理由、そしてそれでも働き続けた背景について、正直に書いてみたいと思います。
私の時短勤務の履歴と働き方の変遷
まず、私の時短勤務の期間と働き方の変化を簡単にご紹介します。
- 長男1歳3ヶ月まで:育休取得
- 長男2歳:時短勤務(6.5時間/9:30〜17:00勤務 → 18:00お迎え)で復帰
- 長男3歳:時短勤務を7時間に延長(9:30〜17:30勤務 → 18:30お迎え)、次男妊娠
- 次男出産:再度育休取得
- 次男10ヶ月・長男5歳:時短勤務(6時間/9:30〜16:30勤務 → 17:30お迎え)で復帰
このように、子どもの成長や家庭の状況に合わせて働き方を変えてきました。
時短勤務の「報われなさ」を感じた瞬間
給与が減っても仕事量は変わらない
時短勤務は、その名の通り労働時間を短縮する制度。
そのため、当然ながら給与も勤務時間に比例して減額されます。
しかし現実には、「仕事量は減らない」「フルタイムと同じ水準の成果を求められる」ということも多く、私はまさにその状況にありました。
特に専門職であるため、担当する業務の内容や責任が変わらず、「フルタイム時と同じだけ働いている感覚なのに、収入は少ない」という状態に。
効率を上げて乗り切ろうと必死でしたが、思うようにいかない日々が続きました。
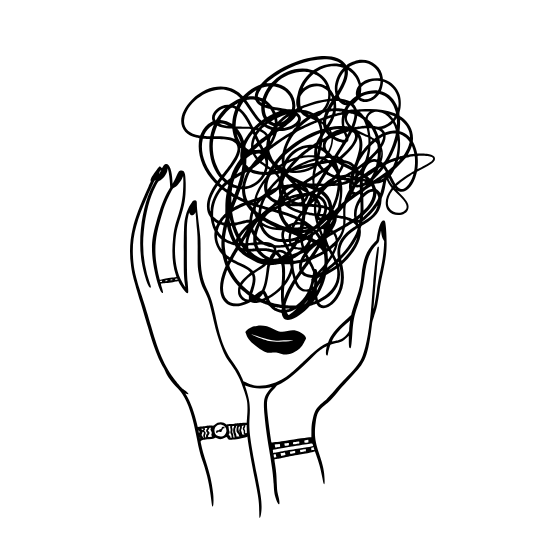
時間に追われると、仕事も遅れがち。
子どもに優しくできない日が増えて、自分を責めてしまうこともありました。
昇進やキャリアへの影響
時短勤務を選んだことで、評価や昇進のチャンスが遠のいたと感じることもあります。
実際、私の職場では役職がついているママ社員は、祖父母のサポートを得ながらフルタイム勤務をしている人ばかりでした。
時短で働いている人が管理職になる例はなく、私はこのまま同期や後輩にどんどん差をつけられていくのでは…という不安を常に抱えていました。
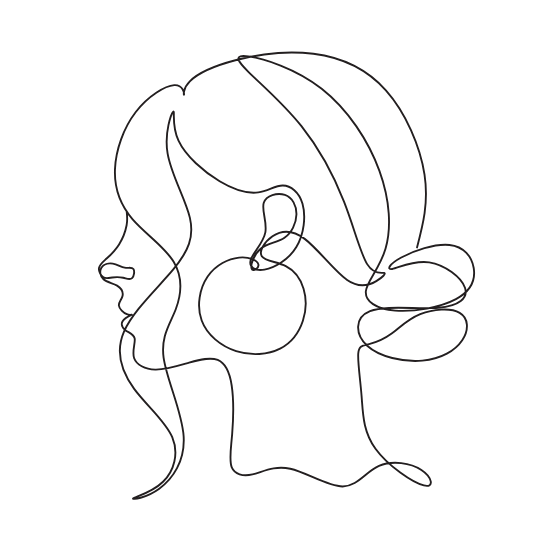
もちろん、キャリアにこだわらない働き方もありますが
正社員として働く以上、「年数が経てば求められることも増える」のが現実。
ずっと同じ仕事を同じスタンスで続けるのは、どこかで限界が来ると感じていました。
「働き続けるか迷ったとき」に考えたこと

家計と生活のバランスをどう取る?
時短勤務による収入減が家計に与える影響も、現実的な問題です。
配偶者の収入や支出の見直し、時には延長保育や家事代行、ベビーシッターなどの外部支援を検討しながら、我が家も何とか乗り切ってきました。
近年は、時短勤務による減収を補う給付金制度も登場していて、条件を満たせば受給できるケースもあります。
※詳しくは自治体や雇用保険の公式サイトで確認を。
ワークライフバランスは本当に取れるのか?
「時短=余裕ができる」と思われがちですが、実際にやってみると、余裕どころか“常に時間に追われている”感覚に陥ります。
例えば、私の平日のスケジュールはこんな感じでした。
朝は6時過ぎに起きて、子どもたちの朝食・保育園の支度・自分の準備をこなして家を出発。
出社後は限られた勤務時間の中で、通常通りの仕事をこなします。
15時半を過ぎると「そろそろ切り上げて退社しないと保育園に間に合わない…」という焦りが頭をよぎり、16時半に退勤して猛ダッシュで二人のお迎えへ。
別々の保育園に通わせていたこともあり、保育園をはしご。
家に帰れば夕食づくり、子どもとの時間、寝かしつけ…と、休む間もなく次のタスクが続きます。
一息つけるのは、子どもが寝たあと、21時過ぎ。それも洗濯や翌日の準備がある日には、あっという間に寝落ちしてしまうことも。
この生活を続けながら、ふと「これのどこが“時短”なんだろう」と思ったこともありました。
勤務時間は短いのに、心の余裕は全然ない。むしろ、「早く帰る分、成果を出さなきゃ」と焦り、仕事にも手を抜けず、家庭にも申し訳なさを感じて自己嫌悪に…。
結局、ワークライフバランスを保つには、「短時間で何とかする私」だけでは無理だと痛感しました。
家族の協力はもちろん、「この時間までに業務を終えるためにどうするか」を一緒に考えてくれる職場の理解も不可欠です。
業務量や責任の調整、在宅勤務や柔軟な働き方の制度など、周囲との連携があって初めて、ようやく“バランス”が取れるのだと思います。
時短勤務でも働きやすくするためにできること
時短勤務は、確かに家庭との両立を助けてくれる制度ですが、「時間が短くなる=働きやすくなる」とは限りません。むしろ、限られた時間で同じ成果を求められたり、周囲との調整に疲れてしまうことも多々あります。
そんな中でも、少しでも働きやすくするために私が実際に試した工夫や、今振り返って「これは効果的だった」と思えるポイントをご紹介します。

業務の「見える化」で、優先順位をはっきりさせる
時短勤務では、1日の中で使える時間が限られているため、仕事の優先順位を明確にすることが最重要です。
私は毎朝、「今日やること」「今日じゃなくてもいいこと」をにToDoリスト書き出していました。
ToDoリストにしておくことで、急な呼び出しや子どもの体調不良で予定が狂っても、最小限の影響で済ませることができます。
また、上司にも「この仕事に今どれくらい時間をかけているか」「どこがボトルネックになっているか」を共有するようにし、無理が出ている部分は見直してもらえるよう相談していました。
見える化は、自分自身のマネジメントだけでなく、上司との信頼関係を築くうえでも有効です。
在宅勤務やフレックスタイムなど、制度の併用を検討する
もし職場に在宅勤務やフレックス制度があるなら、遠慮せず積極的に活用することがポイントです。
私の場合、残念ながらフレックス制度がなく、在宅勤務は週2日許されている会社だったので、「◯曜日と◯曜日は在宅にする」と決めることで、精神的な余裕がグッと増えました。
在宅勤務は、通勤時間がなくなるだけで体力的にも精神的にもかなり違います。
保育園のお迎えまでの「隙間時間」で家事を済ませられるようになったのも、想像以上に助かりました。
「時短勤務だから仕方ない」と自分を責めすぎない
時短勤務だと、「成果が出せないのは自分のせい」「評価が低いのは時間が足りないせい」と、自分を責めてしまいがちです。
でも本当は、制度だけでなく、職場の理解や業務の設計次第でも働きやすさは変わってくるんですよね。
私もある時期、「もっと頑張らないと」と無理をして体調を崩し、結果的に迷惑をかけてしまったことがありました。
それ以来、必要以上に自分を責めるのをやめ、「必要なことは声に出して伝える」「休むときはしっかり休む」という姿勢に切り替えたことで、気持ちも仕事の回り方もかなり楽になりました。
家庭内のタスクも“見える化”して、パートナーと共有を
意外と見落とされがちなのが、家庭内の負担です。
時短勤務をしていると、「家のことは私がやるべき」と思い込みがちですが、それで心身がすり減ってしまっては意味がありません。
我が家では、家事や育児の役割は、できる方ができることをやるスタンスを共有しています。
子供の行事はGoogleカレンダーで共有し、仕事の調整が付けば保護者会の参加や病院の付き添いにパパもフル稼働です。
「朝の送りはパパ担当」「夕飯はママ担当」など明確に分かれているタスクもありますが、柔軟に状況に合わせて変えています。
まとめ:時短勤務がつらいと感じたら
時短勤務は、育児と両立しながら働くための有効な制度です。
しかし、働き方や職種によっては「思っていたよりも大変」「報われていない」と感じることもあります。
それでも私が働き続けたのは、「社会との接点を持ち続けたかったから」。
自分のキャリアや成長を諦めたくなかったからです。
大切なのは、「何を優先したいのか」を自分で明確にしながら、柔軟に働き方を見直すことだと思います。
悩んでいるママたちに、少しでもヒントになりますように。