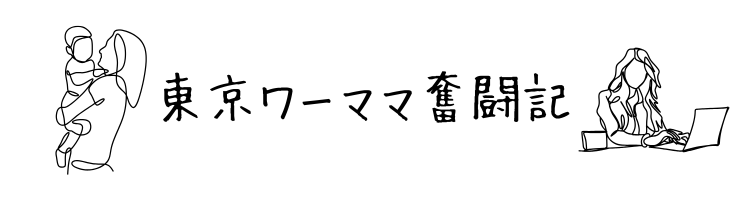保育園では「ちょっと気になる子」と見られていた息子。
集団が苦手で、目立ちやすくて、でも家ではそこまで困らない。
発達障害ではないけれど、なんだか周りとちがう・・・。
そんな息子が、小1で受けた発達検査でIQ127とわかりました。
「ちょっと特性がある子」と過ごしてきた数年間を、振り返ってみます。
集団になじめない?落ち着かない?保育園時代
2歳後半からの違和感
息子が保育園に通い始めてしばらく経った2歳後半のころ、先生から「落ち着きがない」「好きなことをやめられない」など、集団行動の難しさを指摘されることが増えました。
私も「ちょっと違うかも…?」と感じるように。
でも、家庭ではそこまで困ることはなく、様子を見ていました。
年少~年中:フレンドリーすぎて距離が近い?成長とのギャップに悩んだ時期
年少になると、「集団指示が入らない」「お友達との距離感が近すぎる」といった行動が目立つように。
息子は人懐っこく、誰とでも話したがるタイプ。
だけど、その“良さ”が集団では浮いてしまう場面も多く、親としては複雑な思いでした。
年中では加配がつき、発達支援センターに相談。
発達検査の結果は年齢以上の発達水準で、心理士さんからは「問題なし」「家庭で様子見を」との見立て。
療育は見送ることになりました。
4歳の不安と涙…加配を勧められた日を忘れない
4歳のころが一番手がかかった、と今でも思います。
園から「加配をつけてはどうか」と言われたとき、私は保育士さんの前で思わず涙が出てしまいました。
なぜあの時、涙が出たのか。今でもはっきりとは分かりません。
ただ、どこかで「普通であってほしい」と願っていた自分がいたのかもしれません。不安と戸惑いでいっぱいだったことだけは、今もよく覚えています。
年長で再び療育の勧め。通い始めて感じたこと
年長になっても加配は継続。
小学校進学が近づく中で、園から再び療育の勧めがありました。
園では「親が療育に否定的」と思われていたようでしたが、実際には心理士さんからの積極的な勧めがなかっただけ。
必要であれば行かせたいと思っていたことを丁寧に伝え、誤解は解けました。
5歳の夏から、週1回の療育に通い始めました。
集団と個別のプログラムがあり、親子で協力しながら通う日々。
夫と交代で平日に半休を取り、何とか通い切りました。
療育に通ってみて驚いたのは、「いろんな子がいる」ということ。
発達障害という言葉で一括りにできるような場所ではなく、その子の困りごとに向き合う場所なのだと実感しました。
小学校入学―「違い」をうまくつなぐ工夫
“伝えておいてよかった” 就学前の引き継ぎの力
保育園と小学校をつなぐ「就学前引き継ぎ」の仕組みを活用し、息子の特性を学校に伝えました。
入学前に校長先生やスクールカウンセラーと話す機会があり、保育園での様子をしっかり伝えることができました。
担任はベテランの先生で、最初はクラスでいくつかトラブルもありましたが、少しずつ環境にも慣れ、学校は息子にとって楽しい場所になっていきました。
勉強面には全く問題なく、「うまく環境が合えば、ぐんぐん伸びるタイプ」と言われました。
家でも学校でも、感情のコントロールや距離感などは少しずつ成長し、我慢できる場面が増えていったと感じます。
小学2年で通級へ。このときIQ127と診断された
2年生への進級時、学校側から「素直なうちにソーシャルスキルを学ぶ機会があると良い」と提案があり、通級指導教室へつなげてもらいました。
このとき、知能検査を受けたところ、IQ127という結果が出ました。
「やっぱり頭の回転は早いんだな」と納得する一方で、それが育てにくさの理由とすぐに結びつくわけではない、とも感じました。
IQよりも「今の子どもをどう支えるか」
IQという数値だけでは、子どもの本質は見えてきません。
息子は、自分の思いが強く、情熱的。
人との距離が近いこともありますが、人の気持ちが分からないわけではないのです。
成長に伴って、少しずつ「我慢できる」「折り合いをつけられる」力が育ってきたと感じています。
だからこそ、ラベルや診断名にとらわれすぎず、その子の今と向き合う姿勢が大切なんだと思います。
「ちょっと気になる子」の親御さんへ伝えたいこと
発達障害ではないけれど、ちょっと育てにくい。
「なんだか周りと違う気がするけれど、どうすればいいのか分からない」
そんな風に感じること、ありませんか?
わが家もそうでした。
はっきりと診断が出るわけでもないからこそ、迷いや不安が大きくなる。
でも今振り返ると、「少し気になる」時点で誰かに相談することは、決して早すぎることではなかったと思います。
子どものためだけでなく、親自身が安心するためにも。
療育や支援は、「困っている人のため」だけのものではなく、子育てを少し楽にしてくれる“味方”でもあります。
困った時は、迷わず声をあげていい。
そう思えるようになるまで、時間はかかりましたが・・・今は心からそう感じています。